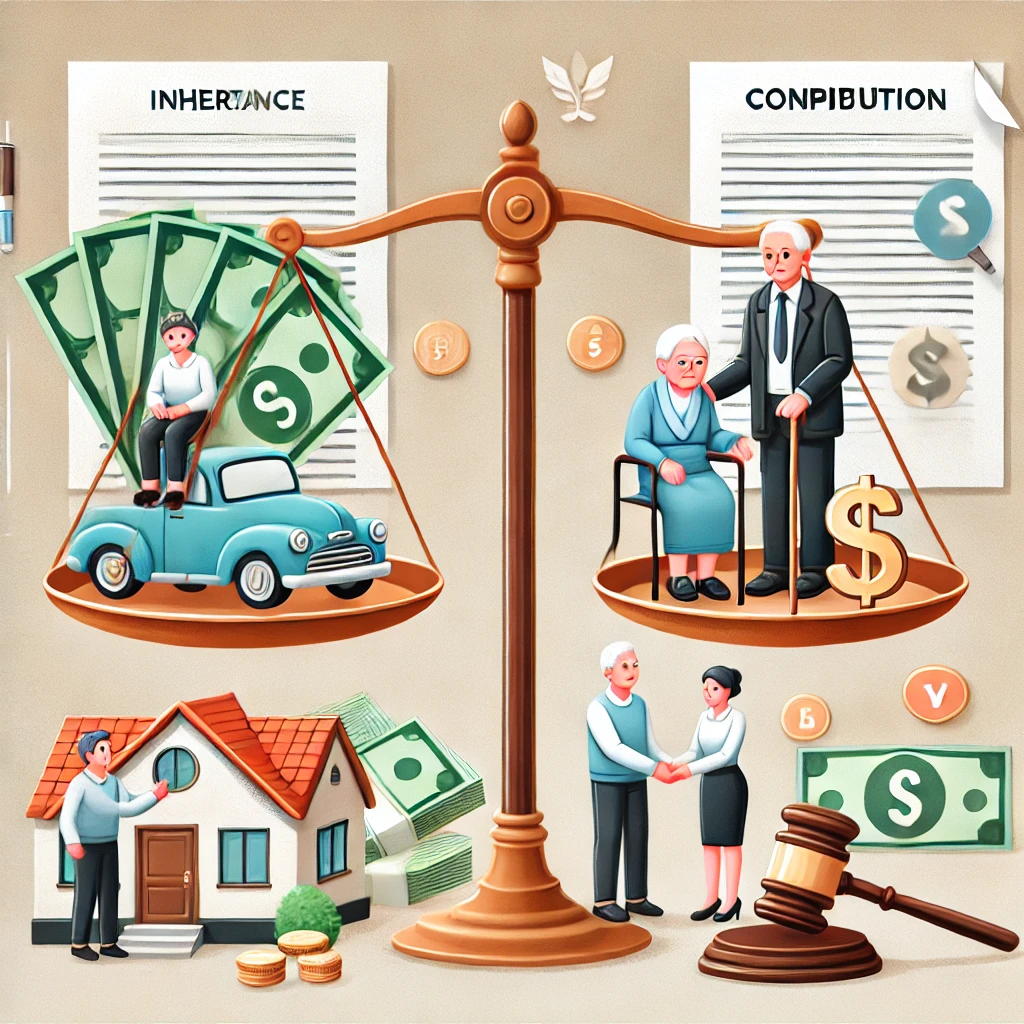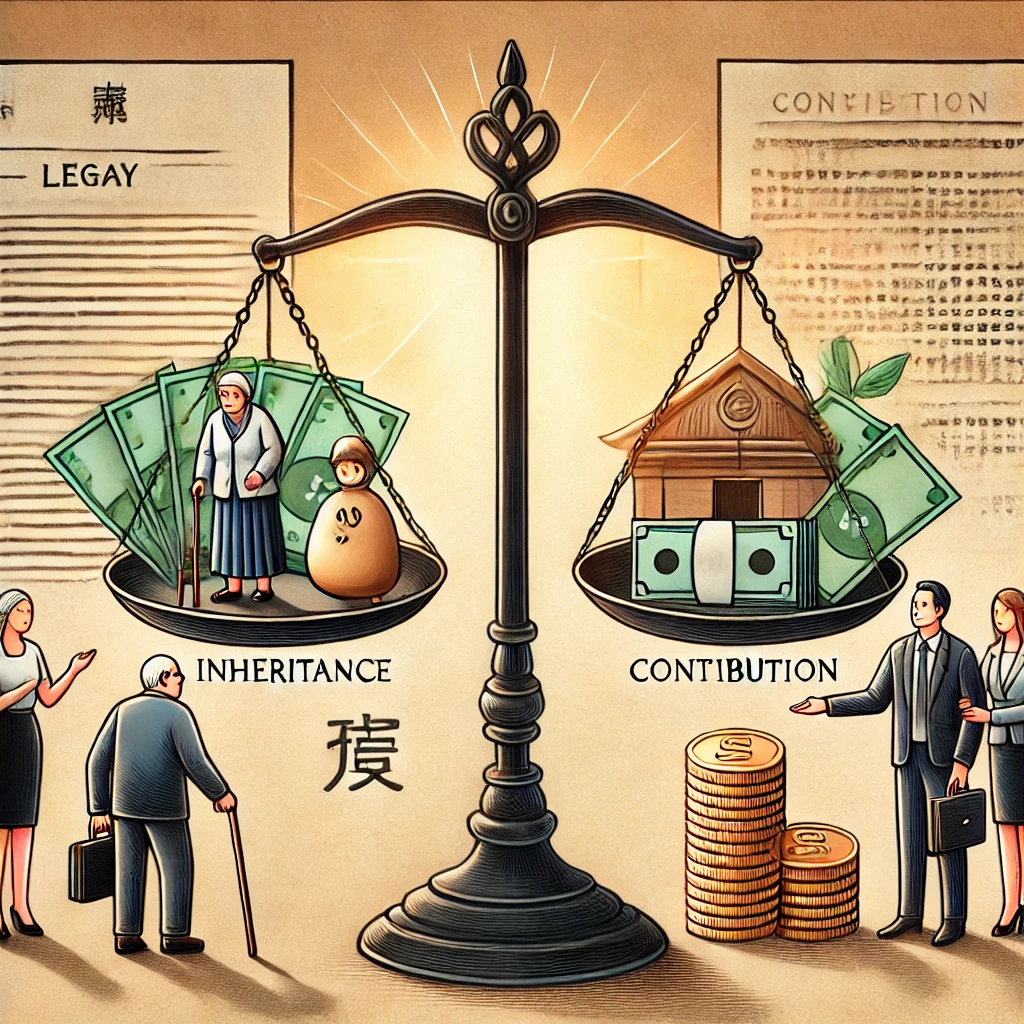こんにちは。「難解な法律用語をわかりやすく伝えること」をモットーにしている弁護士の小田誠です。
相続が発生したとき、被相続人(亡くなった方)の財産は法定相続人に分配されます。しかし、相続人の中には「自分は特別に貢献したのに、同じ割合で分けられるのは納得できない」と感じる方もいるかもしれません。そうした場合に考慮されるのが「寄与分」です。
今回は、寄与分とは何か、その要件や具体的な計算方法について弁護士が解説します。
目次
1. 寄与分とは?
寄与分とは、被相続人の財産の維持や増加に特別な貢献をした相続人に対して、その貢献を考慮して相続分を増やす制度です。これは民法第904条の2に規定されており、適用されるためには一定の条件を満たす必要があります。
2. 寄与分が認められるための要件
寄与分が認められるためには、以下の要件を満たす必要があります。
(1) 相続人であること
寄与分を主張できるのは、被相続人の相続人に限られます。たとえば、息子の妻が義父の介護をした場合でも、息子の妻自身は相続人ではないため寄与分を主張することはできません(ただし、息子が代わりに主張することは可能です)。
被相続人以外の親族が自身の貢献度を主張できるのは「特別寄与」という制度です。
こちらについて知りたい方は以下の記事をご覧ください。
(2) 特別の寄与があること
単なる親族としての通常の扶養義務や介護ではなく、「特別な貢献」が求められます。具体的には、以下のようなケースが該当します。
- 被相続人の事業を無償で手伝った
- 被相続人の医療費を長年にわたり負担した
- 被相続人の介護を継続的に行った
- 被相続人の不動産の管理・維持に貢献した
(3) 被相続人の財産の維持・増加に貢献したこと
寄与行為によって、被相続人の財産が増えたり、減るのを防いだことが必要です。
(4) 無償または著しく低い対価で行われたこと
寄与分が認められるには、報酬を受け取っていない、あるいは非常に低い報酬しかもらっていない場合に限られます。
3. 寄与分の具体的な計算方法
寄与分は、相続財産の中から寄与者の貢献分を評価し、それを控除した残りを他の相続人と分配する形で決められます。具体例を見ていきましょう。
【計算例】
- 被相続人の遺産総額:3,000万円
- 相続人:長男・次男の2人
- 長男が被相続人の介護を10年間無償で行ったため、寄与分として500万円が認められた
この場合、まず遺産3,000万円から寄与分500万円を控除し、残りの2,500万円を法定相続分(1/2ずつ)で分けます。
したがって、
- 長男の取得額:500万円(寄与分)+1,250万円(法定相続分)=1,750万円
- 次男の取得額:1,250万円
となります。
4. 寄与分を主張するには?
寄与分を主張するには、相続人間の協議で合意するか、家庭裁判所に調停・審判を申し立てる必要があります。話し合いで合意できない場合は、家庭裁判所が寄与分を決定します。
主張を通すためには、以下のような証拠を用意するとよいでしょう。
- 介護日誌や医療費の領収書
- 事業への貢献を証明する契約書や業務記録
- 他の相続人や第三者の証言
家庭裁判所に寄与分を定める処分調停を申し立てる場合、以下の裁判所のHPが参考になりますのでリンクを貼っておきます。
5. まとめ
寄与分は、相続人の中でも特別に貢献した人が正当な評価を受けるための制度です。ただし、認められるためには一定の条件を満たし、適切な証拠を用意する必要があります。
相続の話し合いは感情的になりがちですが、法的な知識を持つことで冷静に対処できます。寄与分について不安がある場合は、専門の弁護士に相談することをおすすめします。
相続や寄与分についてお困りの方は、お気軽にご相談ください。専門家があなたの権利をしっかりとサポートします。