遺言書は、生前に人が自分の財産の分け方を遺族人に的確に伝える手段であり、遺産分割に伴う遺族への負担を軽減する重要なツールです。しかしながら、実は遺言書があるのに紛争になり、何年間も遺産分割調停をする羽目になったケースを私は何度も見てきました。そこで、このコラムでは、遺言書があるのに紛争になったケースをご紹介し、どのようにしてこれらを回避できるかを解説します。
目次
遺言書の種類と基本的な要件
遺言書と言っても実は民法上3種類あります。
その内、実務上よく使われるのは下記の2種類です。
自筆証書遺言
自筆証書遺言は、遺言者が全文を自手で書き、日付と氏名を記入し、署名押印することで成立します。この方法の利点は、誰の助けも借りずにプライベートに遺言を作成できることですが、形式の誤りや表現の不明確さが無効の原因となることがあります。
公正証書遺言
公正証書遺言は、公証人と証人二人の立ち会いのもとで遺言内容を口述し、公証人がそれを文書化します。この遺言形式は、遺言の保管と法的有効性を公証人が保証するため、紛失や偽造のリスクが非常に低く、訴訟のリスクも減少します。
遺言書があるのに紛争になるケース
以下では、私が経験した遺言書があるのに紛争になったケースをご紹介します。
遺言書が法的に無効となったケース
意思能力がないケース
遺言書が存在しても、法的に無効となってしまっては元も子もありません。
遺言書作成前に重度のアルツハイマーとの診断がなされており、死亡後にその診断書を法定相続人が提出してきたケースがありました。遺言書は法律文書のため、意思能力がない状態で作成された遺言書は無効となります。
遺言書は高齢になってから作成されることが多いですし、アルツハイマーだった場合、周囲から見ても明らかなことが多いので、意思能力を争われるケースは散見されます。
遺言書が法律の要件を満たしていないケース
自筆証書遺言に多いケースです。
自筆証書遺言は誰でも自宅で気軽に作成できる反面、公正証書遺言と異なり、公証人が法律要件の充足性についてチェックしてくれるわけではないため、法律によって決められたルールを守ることができていない場合があります。
自筆証書遺言は全文自書する必要があり、財産目録を除いて、パソコン入力することが法律上許されていません(甚だ時代遅れだとは思いますが)。そのため、本文をワードで作成した時点で無効です。また、署名押印を忘れても無効です。作成日付がなくても無効です。
このように自筆証書遺言は気軽に作成できる反面、落とし穴が多いのが難点です。
遺言書は有効だけど紛争になったケース
遺言書が法的に有効であればそれで安心!
実は、というわけではありません。
実際、私は遺言書が存在し、法的に有効なのに紛争になったケースを何度も目の当たりにしてきました。
以下、遺言書が存在し、法的に有効なのに紛争になったケースをご紹介します。
遺産が漏れている
遺言書には、一般的に財産目録を付けて、遺言者の財産を網羅的に記載し、誰にどの財産を取得させるか記載することが多いです。
しかしながら、まれに遺産の一部が漏れているケースがあります。
遺言書を作成した後に取得した財産であったり、そもそも存在を忘れていた財産などです。
このような場合、通常「その他の財産は★★に相続させる」などという条項を設けておき、対応するのですが、私が経験したケースでは、遺産の脱漏+上記条項無のために、非常に価値の高い不動産の相続を巡って紛争になった事件がありました。
遺産相続事件に詳しい弁護士が作成した遺言書ではなかったため、起きた事件と言ってよい事件だったと思います。
遺留分に配慮されていない
遺言書の内容は、遺言者によって実に様々です。
中でもよく目にするのが、特定の相続人に全ての財産を相続させる内容の遺言です。
例えば、以下のようなケースです。
子供が3人いて、上の子二人は結婚して遠方にいる。一番下の子は結婚せずに母に寄り添い、同居して介護をしてきました。父はすでに亡くなっているため、母は一番下の子に全ての財産を相続させる内容の遺言書を作成しました。
母が亡くなり、後日遺言書の存在を知った上の子二人は、遺留分侵害額請求権を行使する旨の配達証明付き内容証明郵便を下の子宛に送ってきました。
というようなケースです。
法定相続人には、たとえ遺言書があったとしても、最低限もらえる遺産の範囲が存在します。
これを遺留分といい、被相続人死亡後に行使することによって効力が生じます(遺留分については別のコラムで詳述します)。
兄弟間の仲が良く、相続の際に遺留分侵害額請求権の行使がなされないことが明らかなケースを除いて、紛争の芽を摘んでおくというという観点からは、遺留分に配慮した遺言書を作成しておいた方が良いでしょう。
遺産分割方法の理由が記載されていない
遺言書には一般的になぜそのような分け方をするのか記載することはあまりありません。
しかしながら、法定相続人間で一見して不平等な分け方をする場合(特定の人が多くの遺産をもらう場合)、その理由について明記しておいた方が紛争の可能性は小さくなるでしょう。
たとえば、「★★は生前、長い間付き添い看護してくれた。そのため、★★には多めに財産を分与する」とか「★★は大学院まで行かせたが、●●は大学にさえ行かせられなかった。そのため、●●には多めに財産を残す」などです。
当事者にとって納得感が出るように配慮してあげるのがよいでしょう。
不動産の権利関係に配慮していない
不動産は、「法律問題の宝庫」と言われるくらい色々な紛争・揉め事を引き起こします。
そのため、不動産に関わる権利関係をきれいに整理しておかなければ、遺言書があっても紛争を防止できません。
たとえば、「土地をAに、その土地上にある建物をBとCの共有にする」といった遺言書をたまに見ます。その建物には、Cしか住んでいないケースだと、AやBはCから賃料をもらえるのでしょうか。AやBが亡くなった場合、権利関係はどうなるのでしょうか。
ちょっと考えただけでも頭が痛くなりそうです。
不動産は共有にしておくと、後々大きな揉め事に発展していくことが多いので、基本は単独所有にすべきです。また、居住者と所有者はできる限り一致させておいた方がよいでしょう。
対応策
以下では、上記の問題点を避ける対応策を記載します。
法的に無効な遺言書を避ける対応策
自筆証書遺言を選択せず、公正証書遺言を選択すべきです。
公正証書遺言が要件不充足によって無効となったケースは見たことがありません。
また、アルツハイマーかどうかのチェックも事前に促されるため、意志無能力による無効も回避できる可能性が高いです。
内容面の不備を避ける対応策
完結に記載しますと、全ての遺産を遺産目録に網羅的に記載すること、遺留分に配慮すること、不動産の権利関係を整理すること、遺産分割方法の理由を遺言書の中で説明することに配慮しておけば、大方の問題には対応できると思います。
まとめ
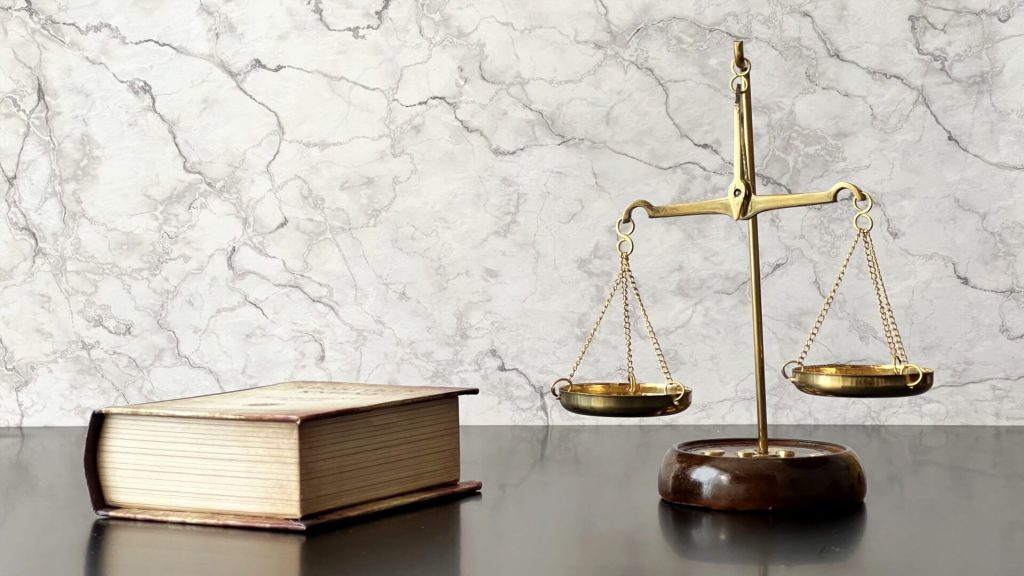
遺言書の作成は、個人の最後の意志を正確に表現する手段です。自筆証書遺言や公正証書遺言の選択、法的要件の充足、内容面の不備の回避を通じて、遺言の有効性を保証し、未来の紛争を防ぐためには専門家のアドバイスが不可欠です。適切な手続きを経ることで、遺言が本当に意図した通りに実行されることを確実にします。
私が一番お勧めするのは以下の点です。
- 遺産をどう分けるかについてとにかくよく考えること
- 悩んでも分からない場合は、相続事件に精通した弁護士に相談すること
遺言書作成に関するご相談やサポートが必要な際には、いつでも私にご連絡ください。あなたの大切な意志が正確に反映されるよう、全力でサポートさせていただきます。


