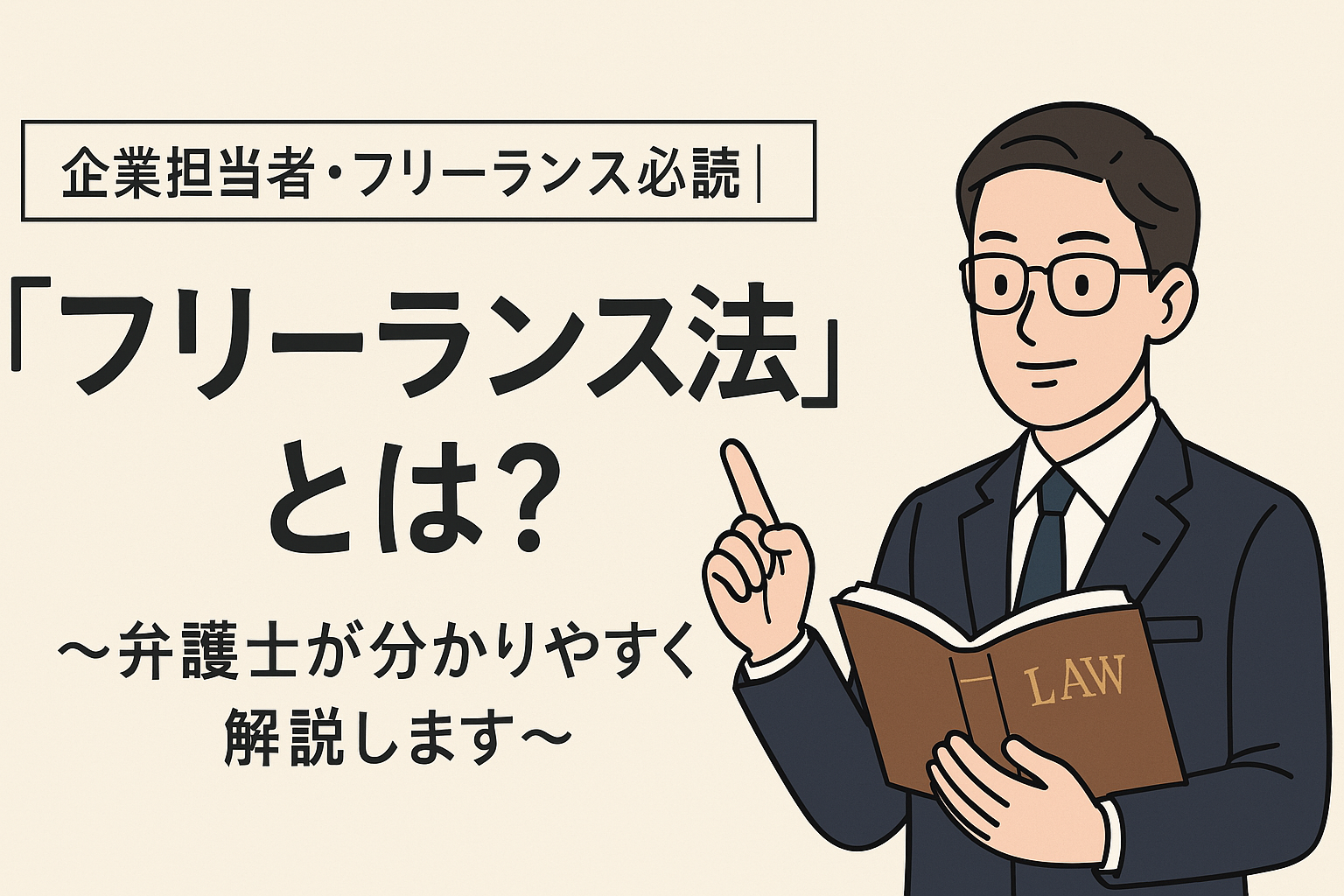こんにちは。企業法務を中心に活動している弁護士の小田誠です。
2023年に成立し、2024年11月に施行予定の「フリーランス法(※正式名称:特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律)」をご存じでしょうか?
この法律、今後のフリーランス活用や委託取引に関わる企業にとって非常に重要です。
本記事では、企業の法務担当者・経営者・そしてフリーランスとして活動されている方にも向けて、**「フリーランス法って何?」「自社に影響あるの?」「具体的に何をすればいいの?」**という疑問にお答えしていきます。
さらに詳しく知りたい方のため、公正取引委員会のHP記事のリンクを貼っておきます。
「フリーランス法とは?」
目次
1.そもそも「フリーランス法」とは?
この法律の目的を一言で言えば、
**「フリーランスとの取引を適正にしましょう」**ということです。
背景には、フリーランスが業務委託という形で企業と取引する際に、立場が弱くなりがちだという問題があります。
例えば以下のようなケース、思い当たる方もいるかもしれません。
- 契約書がないまま仕事開始
- 報酬の支払いが異常に遅い、あるいは支払われない
- 突然のキャンセルで収入ゼロ
こうした「取引上の不公正」からフリーランスを保護し、健全な経済活動を促進するのがこの法律の狙いです。
2.誰が対象になるの?
法律上のキーワードは「特定受託事業者」と「発注事業者」です。
✅ 特定受託事業者(=保護される側)
いわゆるフリーランス(=個人で業務を受託する人)のうち、
「従業員を雇わずに、他人から業務委託を受けて事業を行う個人」が該当します。
例:デザイナー、ライター、エンジニア、コンサルなど
✅ 発注事業者(=義務を負う側)
フリーランスに仕事を委託する企業や団体、個人事業主です。
2−1.【注意】フリーランス法の適用除外となるケース
以下のような場合、たとえ“フリーランス的な働き方”をしていても、本法律の保護対象には該当しません。注意が必要です。
❌ 従業員を雇っている個人事業主
たとえば、アシスタントや事務員などを雇用契約で雇っている場合、その個人事業主は「特定受託事業者」に当たりません。
➤ 少人数の会社(いわゆる“ひとり社長”)と混同しやすいですが、「法人化していないが人を雇っている」場合も対象外です。
❌ 法人(例:合同会社、株式会社など)
法人格を持つ事業者(たとえ実質的にひとりで経営していても)は対象外です。
法人であれば、下請法など別のルールが適用されることになります。
❌ 業務委託ではなく、雇用契約に基づく労働者
例えば、「個人事業主」として登録していても、実態が企業の指揮命令のもとで働く場合は、法律上「労働者」とみなされる可能性があり、労基法等の適用が問題になります。
3.企業が守るべき主な義務
(1)業務委託の際の書面交付義務
仕事を発注する際に、契約書や発注書を交付する義務があります。
口約束やSlackだけのやり取りでは不十分です。
※内容には、業務内容、報酬額、支払期日などの記載が必要。
(2)報酬の支払い義務(60日以内)
報酬は、業務完了から原則60日以内に支払う必要があります。
これまで「検収が長い」「社内の締め処理の関係で…」などで先延ばしにされていた部分に明確な期限が設けられました。
(3)不利益取り扱いの禁止
「妊娠したから契約終了」「クレームを入れたから次の発注をしない」
といった不利益な取り扱いは、明確に禁止されています。
4.違反するとどうなる?
行政指導や勧告・公表・命令の対象になります。
命令違反の場合、最大で50万円の過料も。
今後、企業のレピュテーションリスク(評判リスク)にもつながる可能性があります。
5.企業が今すぐ見直すべきポイントは?
✅ 契約書や発注書を交付しているか?
✅ 報酬の支払いサイトは60日以内か?
✅ 妊娠や育児などを理由に取引を打ち切っていないか?
✅ 「準委任」契約になっている場合の労務管理は適正か?
特に「準委任」で実質的に労働者に近い働き方をしているケースでは、
労基法や社保の適用リスクも出てきます。
まとめ
フリーランス法は、企業がフリーランスに対して適切な取引を行っているかを問う法律です。
一部の「下請法」「労基法」とも接点があるので、既存の契約・運用を放置しておくとリスクになる可能性も。
「うちはあまり関係ない」と思っていた企業ほど、実は対応が必要だった…というケースも少なくありません。
法務・総務・人事部門が連携して、今のうちに見直しをしておくことをおすすめします。
もしご不安な点がある場合は、顧問弁護士や法務の専門家と一度棚卸ししてみてくださいね。
私もフリーランス契約のリーガルチェック等を多くご相談いただいていますので、お気軽にお問い合わせください。