相続の世界ではよく登場する遺留分ですが、法律に詳しくない人からすると「よくわからない」、「そもそも初めて聞いた」という人もいるでしょう。
今日は、遺留分をアンパンマンに例えて解説することを試みたいと思います笑
目次
遺留分とは?
まず、そもそも遺留分とは何なのかというところからご説明します。
遺留分についてAIに聞いたところ、以下の回答を得ました。
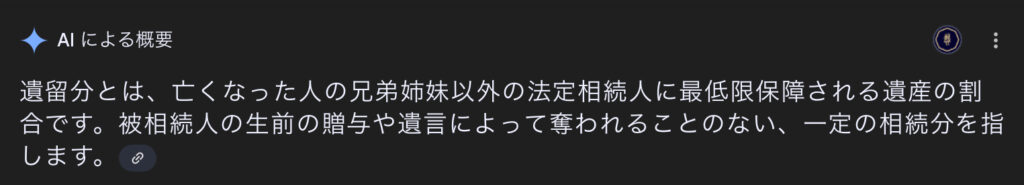
この回答は正しいと思います。
遺留分は、兄弟姉妹以外の相続人にのみ認められます。
具体的な遺留分の割合は、今回は割愛しますが基本的に法定相続分の2分の1です。
※尊属のみが相続人の場合のみ3分の1となります。
遺留分が問題となるのはどんなとき?
遺留分が問題となるのは、遺言書が存在し、かつ法定相続人の遺留分が侵害されている場合です。
難しくなってきましたが、できるだけ分かりやすく解説していくのでご安心ください。
まず、大前提として、遺留分が問題となるのは遺言書がある場合のみです。
遺言書がなければ基本的に法定相続分に従って、遺産分割がなされるので、遺留分は問題となりません。
そして、遺言書によって、遺留分が侵害されている場面で遺留分は問題となります。
どういうことかというと、例えば、夫が亡くなり、妻と子供一人が相続人であるとします。
夫は働き盛りで亡くなり、専業主婦の妻と幼い子供を残して亡くなりました。
ところが、夫は、生前、スナックの若い女の子に入れ上げ、遺産を全てその子に譲る内容の遺言書を残していました。専業主婦の妻と幼い子供は、この先どうやって生活していけば良いのでしょうか?
というような場面で問題となります。
遺留分は残された遺族の最低限度の取り分を保障する意味合いで保護されているものです。
上記の例では、妻と子供は遺産の50%をスナックの女性から取り返すことができるのです。
この侵害された遺留分を取り返す権利を、遺留分侵害額請求権といいます。
遺留分侵害額請求権とは?
今日の本丸、遺留分侵害額請求権について解説していきます。
遺留分侵害額請求権のイメージ
遺留分侵害額請求権のイメージを持ってもらうために、ここでアンパンマンに登場してもらいましょう。
先ほどの例で、妻子が持っている遺留分の大きさをアンパンマンの顔一個分だとします。
かつて、遺留分を取り返す権利のことを遺留分減殺請求権1と呼んでいました。
法律の世界で出てくる用語の中でもトップクラスにカッコいい単語なのでしたね。私はすごく好きな法律用語でした。小学生の時に知っていたら、好きな女の子の前で何回も言っていたかもしれません。
もっとも、2019年7月1日から遺留分侵害額請求権に改正されました。
遺留分減殺請求権だった時代は、アンパンマンの顔そのものを取り返す必要がありました。
アンパンマンの顔一個を侵害されているので、アンパンマンの顔一個を取り返すのです。
そのため、遺留分減殺請求権の時代は、アンパンマンの顔はいらんからお金が欲しい!と思っている場合にも、アンパンマンの顔を取り戻さなければなりませんでした。
例えば、相続財産が実家の土地一つしかない場合、侵害された遺留分を取り戻すために(アンパンマンの顔そのものである)土地を共有にしなければならないことも多くあったのです。土地を共有にしても、遺族は全く嬉しくないと思いますが、相手が共有分を買い取ってくれないと現金が手に入らなかったのです。
これに対し、遺留分侵害額請求権は、アンパンマンの顔を取り戻す必要がありません、アンパンマンの顔を取り返す代わりに、その名の通り、侵害されている額、すなわち、アンパンマンの顔一個分の金銭を請求できるようになりました。
そのため、アンパンマンの顔一個が100万円なら、侵害している相手方に対して、100万円を請求できるようになったのです。つまり、遺留分侵害額請求権は、100万円を貸している相手に100万円を請求できるのと同様に、純粋な金銭請求権になったのです。
これは、実務家からするととても画期的な改正でした
相手が支払いを拒む場合、相手の財産に強制執行ができるため、とても使い勝手がよく、強力な権利となったのです
遺留分侵害額請求権のイメージは持てましたか?
遺留分侵害額請求権の押さえておきたい特徴
遺留分は兄弟姉妹以外の相続人の最低限度の保障である、遺留分侵害額請求権は純粋な金銭請求権である、という二つを理解していただけましたら、この記事の目標は達成ですので、以下は興味のある方のみ読んでいただければと思います。
権利行使期間がある
遺留分侵害額請求権には権利行使期間があり、その期間内に行使しなければ消滅します。
その期間は、遺留分が侵害された事実を知ったときから1年、または相続開始後10年です。
大抵は遺言書の内容を知った時に、侵害の事実を知るでしょうから、遺言書を見た時が始期になると思います。
遺留分の具体的な計算は相続財産全ての評価をしなければ算定できませんが、そのような計算を一生懸命やっていたら、すぐに1年の行使期間を過ぎてしまいます。そこで、侵害の事実を知ったらすぐに権利行使すべきです。
めちゃくちゃ簡単に書くと、「私の遺留分があなたに侵害されているので遺留分侵害額請求権を行使します」と書いて配達証明付き内容証明郵便で侵害者宛てに郵送すればOKです。
裁判外で解決しない場合、調停→訴訟となる
遺留分侵害額請求権を拒むことは基本的にできませんから、侵害者に良識のある弁護士がついた場合は、具体的な侵害額の交渉に移行し、話し合いで解決することも多いです。
話し合いで解決しない場合、家庭裁判所に遺留分侵害額調停を申し立てます。
調停の場で、調停委員を交えて解決を図ります。
それでも解決が難しい場合、民事訴訟を提起することになります。
法律上は、調停をまず申し立ててからでないと訴訟はできないことになっています。
もっとも、ある専門書に、相手方が一切話し合いに応じない姿勢を見せている場合などは、いきなり訴訟提起しても裁判所は受理してくれる場合もあると記載されていました(私は経験がありませんが)。
まとめ
最後にまとめです。
- 遺留分は、相続人に対する最低限度の保障である
- 遺留分侵害額請求権は、金銭請求権である(アンパンマンの顔を取り戻さなくていい)
- 遺留分侵害額請求権には、行使期限があるので早めに行使する
いかがだったでしょうか
この記事を読んで、遺留分について理解できた!という方はこの記事を共有していただけると嬉しいです😊
- 「いりゅうぶんげんさいせいきゅうけん」と読みます。「ゲンサツ」ではありません。かつて、リーガルハイというドラマの中でガッキーは、誤って「ゲンサツ」と読んでしまっていました。 ↩︎


