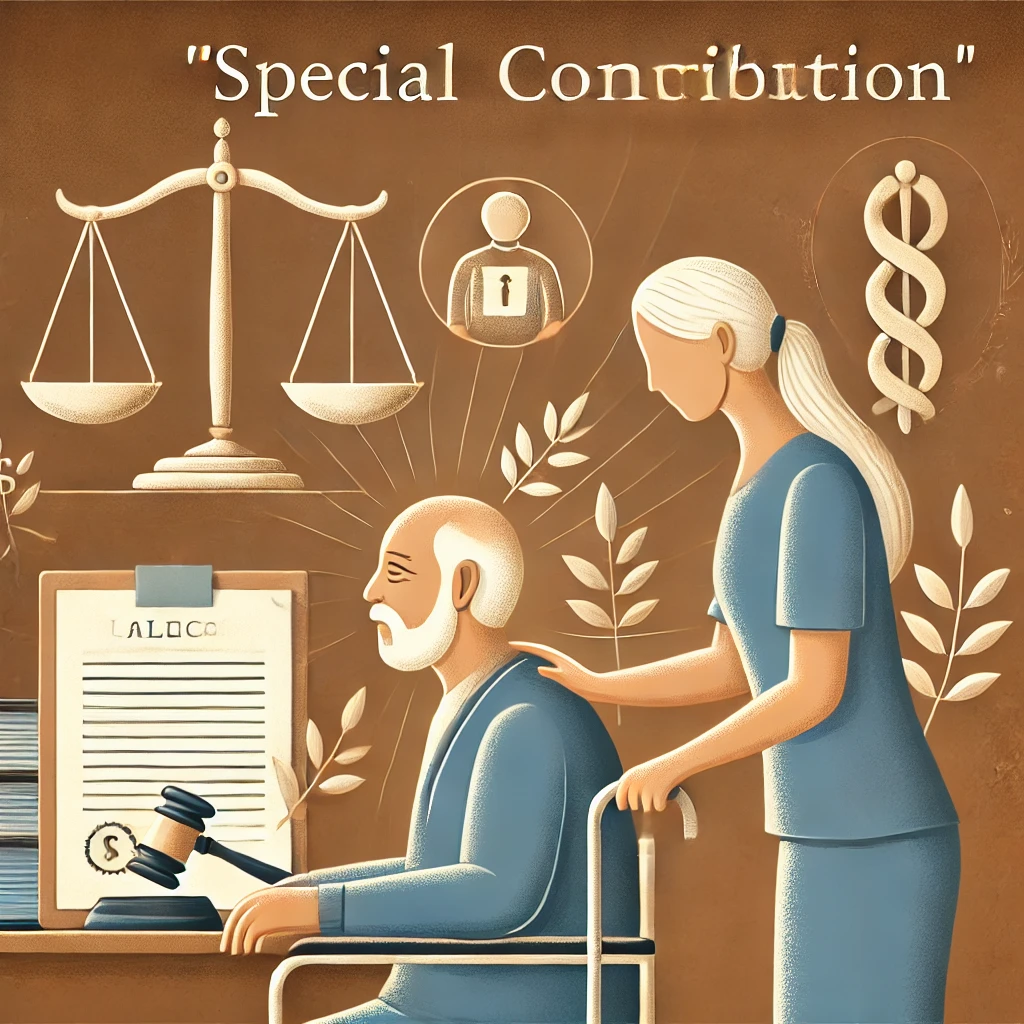こんにちは。弁護士の小田誠です。
相続の場面では、被相続人(亡くなった方)に対して特別な貢献をしたにもかかわらず、法定相続人ではないために相続財産をもらえない…というケースがよくあります。例えば、長年にわたって義父の介護をしてきた長男の妻などが典型例ですね。
こうした不公平を是正するために設けられたのが 「特別寄与制度」 です。2019年7月1日に施行された改正民法で新たに導入されました。
今回は、特別寄与の制度について、弁護士の視点から分かりやすく解説していきます。
法定相続人が特別の貢献をした場合に貢献度を主張する制度について知りたい方は以下の記事をご覧ください。
「寄与分」とは?弁護士が解説
1. 特別寄与とは?
特別寄与とは、 法定相続人ではない人(主に親族)が、被相続人の財産の維持や増加に特別な貢献をした場合に、相続人に対して金銭(特別寄与料)を請求できる制度です。
これまで、法定相続人に該当しない人(例えば長男の妻)は、どれだけ尽くしても相続財産を受け取る権利がありませんでした。しかし、この制度により、一定の条件を満たせば、相続財産の中から金銭を請求できるようになったのです。
2. 特別寄与の対象となる人
特別寄与料を請求できるのは、 被相続人の親族(相続人ではない人) です。
ここでいう「親族」とは、民法上の定義によると、 6親等内の血族・配偶者・3親等内の姻族 です。つまり、例えば以下のような人が該当します。
✅ 長男の妻(義理の父母の介護をしていた)
✅ 被相続人の兄弟姉妹の配偶者(例:義理の弟の妻が尽くしていた)
✅ 被相続人の孫の配偶者(例:祖父母の面倒を見ていた孫の妻)
ただし、 相続人には特別寄与の請求権はありません。たとえば、長男が親の介護をしていた場合は、特別寄与ではなく「寄与分」の問題になります。
3. 特別寄与料を請求できる要件
特別寄与料を請求するためには、以下の要件を満たす必要があります。
- 無償での貢献
- 介護や看護、事業の手伝いなどを 無償またはそれに近い状態 で行っていたこと。
- 例えば、被相続人を介護していたが、介護報酬はもらっていなかったケースなどが該当します。
- 特別の寄与があること
- 「特別」といえるほどの貢献が必要です。
- 例えば、「日常的に家事を手伝っていた」程度では認められにくく、 長期間にわたり、被相続人の生活を支えた などの事情が求められます。
典型的なのは介護でしょう。
- 相続人に対して請求を行うこと
- 特別寄与料は 相続財産から支払われる ため、請求先は相続人です。
- 例えば、長男の妻が義父の介護をしていた場合、義父の相続人(長男や他の兄弟姉妹など)に対して請求することになります。
4. 特別寄与料の額はどう決まる?
特別寄与料の金額は、 相続人と協議 で決めるのが原則です。しかし、話し合いがまとまらない場合は 家庭裁判所に申し立てて決めてもらうこと になります。
判断基準としては、
✅ 寄与の内容(介護の期間、頻度、負担の程度など)
✅ 被相続人の財産の状況
✅ 他に介護や支援をしていた人の有無
などが考慮されます。過去の裁判例を見ると、 100万円~500万円程度の範囲で認められるケースが多い です。
裁判所のHPに「特別寄与に関する処分調停」に関する記事がありますのでリンクを貼っておきます。
5. 特別寄与料の請求期限
特別寄与料は、 相続の開始(被相続人が亡くなった日)を知った時から6か月以内 に請求しなければなりません。また、被相続人の死亡から 10年が経過すると請求権は消滅 します。
「時間が経てば経つほど話がこじれる」ことも多いため、特別寄与料を請求したい場合は、できるだけ早めに動くのが重要です。
6. 特別寄与のトラブルを避けるには?
特別寄与は、相続人にとって「財産を減らされる話」なので、 トラブルになりやすい というのが現実です。スムーズに請求を進めるためには、以下の点に注意しましょう。
✅ 証拠を残しておく
介護日誌、医療費の支払い記録、写真など、 どれだけの貢献をしてきたか証明できるもの を残しておくことが大切です。
✅ 早めに相続人と話し合う
相続発生後ではなく、 生前のうちに相続人と話をしておくこと も有効です。
✅ 弁護士に相談する
特別寄与料の請求は法律的な判断が求められるため、専門家のアドバイスを受けながら進めるとスムーズです。
まとめ
特別寄与制度は、被相続人のために特別な貢献をした人が、正当に評価されるための重要な制度です。
✅ 特別寄与を請求できるのは 相続人ではない親族
✅ 無償の貢献 で 特別な寄与 が必要
✅ 相続人に対して請求 し、協議がまとまらなければ 家庭裁判所へ
✅ 請求期限(6か月) に注意
相続は感情的な対立を生みやすい分野ですが、 法的な権利を正しく理解し、適切に主張することが大切 です。お困りの際は、ぜひ専門家にご相談ください。
特別寄与についてもっと詳しく知りたい方は、お気軽に弁護士までご相談を!