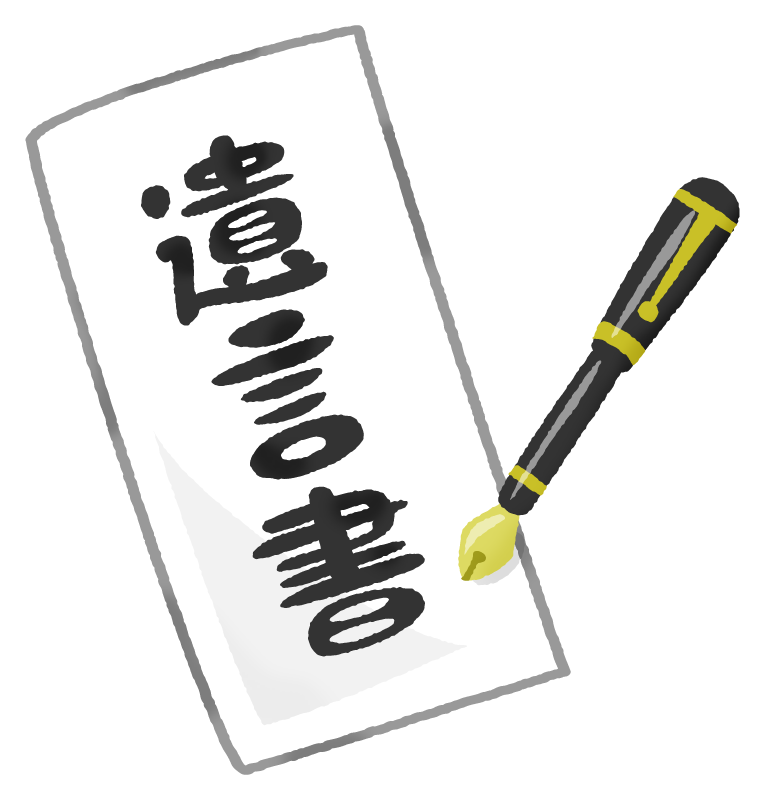今日は、認知症と遺言書の関係について解説していきたいと思います。
目次
大前提:遺言書作成=法律行為
まず大前提として、遺言書の作成は法律行為です。
この「法律行為」という言葉がポイントです。
法律行為は、誰でも自由にできるものではありません。
なぜなら、法律行為には「権利や義務」を発生させる効果があるからです。
当然ながら、その行為がどういう意味を持つのか、自分にどんな影響があるのかをきちんと理解して判断できる能力(=事理弁識能力)が求められます。
例えば、
・車を買う契約
・商売で仕入れをする契約
なども、法律行為です。
これらの行為には「お金を支払う義務」や「物を提供する義務」が発生しますよね。
未成年者と法律行為
特に、事理弁識能力が未熟な未成年者は、両親(親権者)の同意がなければ法律行為はできません。
未成年者が勝手に契約を結んでも、一定の例外を除いて無効になります。
大人にも事理弁識能力は必要
この「事理弁識能力」は、大人にも当然必要です。
ただ、基本的に大人は事理弁識能力があると推定されます。
特殊な事情がなければ、大人が行った法律行為は有効です。
もし、「この人はちょっと頭が悪いから、契約を自由に取り消せる」なんてことになったら、社会は大混乱ですよね。
このため、大人は基本的に「能力あり」と扱われるわけです。
認知症の場合はどうなる?
ところが、認知症にかかると話が変わってきます。
典型的なのが認知症です。
認知症で事理弁識能力を失ってしまった大人は、契約や遺言などの法律行為ができなくなる可能性があります。
認知症の人が遺言書を書くとどうなる?
日本では認知症患者が急増しています。
2022年時点で認知症の高齢者は約443万人。
高齢者の約8人に1人が認知症と言われています。
この傾向は、今後さらに進んでいくでしょう。
ちなみに、私自身も10代の頃、認知症の祖父と約10年同居していた経験があります。
身近な問題として、他人事ではありません。
認知症でも遺言書は書ける?
認知症と一口に言っても、その程度はさまざまです。
- 自分が誰かも分からなくなるほどの重度の認知症
- 物忘れはあるけれど、日常生活は問題なく送れている軽度の認知症
事理弁識能力が失われるレベル(=かなり重度)になると、その状態で書いた遺言書は無効になる可能性があります。
例えば、
- 2020年2月2日付の遺言書が見つかった
- でも2019年12月12日に「重度の認知症」という診断書がある
このようなケースでは、遺言の有効性に後から異議が出される可能性が高くなります。
とはいえ、誰も異議を唱えなければ、そのまま有効になることもあります。
つまり、遺言が「無効かどうか」は争いになるか次第とも言えます。
遺言公正証書なら安心?
遺言書の種類のひとつに「遺言公正証書」があります。
これは公証人が作成に関与するものです。
公証人が直接、遺言者本人と面談して、
- 本当に自分の意思で作るのか
- 内容をきちんと理解しているか
こういった確認を行います。
遺言者本人が、自分の言葉で公証人に説明する必要もあります。
そのため、事理弁識能力がないと作成できません。
もし公証人が「この方、ちょっと判断能力に不安があるな」と思ったら、医師の診断をすすめることもあります。
認知症が進行していると、そもそも公正証書遺言を作ること自体が難しくなります。
※ちなみに、公証人が「事理弁識能力なし」と判断すれば、遺言書は作ってもらえません。
認知症になる前に!早めの遺言書作成を
ここまで見てきたように、認知症になると遺言書作成が難しくなるだけでなく、作成できても無効リスクが高まります。
だからこそ、とにかく早めに遺言書を書くことが重要です。
例えば、
- 子育てが終わって子どもが独立したタイミング
- 定年退職したとき
- 病気などで自分の死を意識したとき
こんな時期が、遺言書作成にぴったりです。
早すぎることはありません。
大切な人へのラストメッセージとして、ぜひ早めに準備しておきましょう。
まとめ
今日のまとめです!
✅ 遺言書作成は法律行為
✅ 法律行為には事理弁識能力が必要
✅ 認知症になると事理弁識能力を失う可能性
✅ 認知症後に作成した遺言書は無効になるリスク
✅ 遺言書はとにかく早めに作成するのが◎
「ためになった!」と思ったら、ぜひSNSなどでシェアしてください!